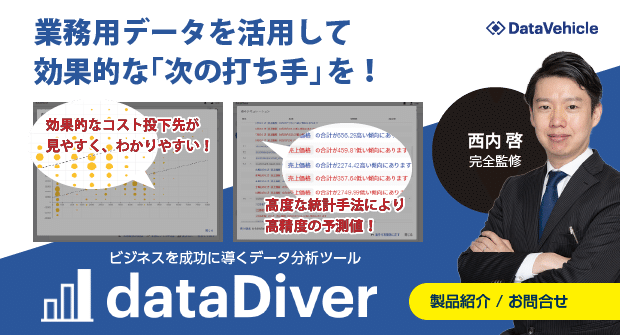「データから直情的・直線的に判断しても成果にはつながらない」日本経済新聞社 山内秀樹氏×西内啓対談 Vol.1
データビークルの最高製品責任者であり統計家の西内啓がデータ活用で成果をあげている企業・組織のキーパーソンの方とデータサイエンスの現実について語り合う対談シリーズ。第三弾は日本経済新聞社に入社以来、「NIKKEI NET」の運営や「日経電子版」の創刊に携わってきた山内秀樹さん。山内さんのこれまでデータとの関わりと、メディアのビッグデータ活用について、お話を伺いました。
シティズンデータサイエンスラボは「データサイエンスを全ての人に」を掲げる株式会社データビークル(https://www.dtvcl.com/)が運営する公式noteです。
感覚ではなく、数字を見てサービスをつくるほうが成果が出る
西内 山内さんはこれまで、統計学についてどのような勉強をしてこられたのでしょうか?
山内 私は東京大学文学部の出身なのですが、専攻していた社会学の社会統計の講義などで、統計的な視点から分析するという勉強をしました。日経新聞に入社してから統計的な素養でビジネスを回すようになったのは、日経電子版が登場し、デジタル化して以降です。もともと新聞社には、データがあるようで無いんです。

西内 新聞の購読に関しては、誰が買っているのかよく分からない状態と聞きますね。
山内 おっしゃるとおりです。新聞を配達している販売店は個人商店ですから、誰が購読しているのか、実際は何部売れているのか、本社ではあずかり知らないのです。このように、広告を売るにしても新聞を販売するにしても、顧客が見えないことによってできていないことが山ほどあるというのは新聞社にとって大きな課題でした。
日経電子版を創刊するときに日経ID(日本経済新聞社グループが提供するサービスの統一ID)をつくったのは、自分たちで顧客属性を捉え、顧客にタッチポイントをつくりたかったためです。
西内 山内さんはそのプロジェクトをはじめる前、社内でどのようなお仕事をされていたんでしょうか?
山内 私が入社した2000年は、まだGoogleも登場したばかりという時代で、インターネットで何をやるかという明確な方針が社内にありませんでした。私は電子版がはじまる以前はNIKKEI NETという無料媒体の制作に携わっていまして、記事の編集からサイトづくりまで、すべての業務をやりました。
NIKKEI NETの規模がだんだん大きくなって仕事を分けていくタイミングで、ウェブサイト自体の戦略・企画を立てる方向にフォーカスをしていって、最終的に自分はNIKKEI NETの企画・開発を担当するようになりました。当時はまだ、社内に「データをどう使うか」という意識がありませんでしたので、最適化をするためのアクセス解析ツールを導入するよう説得したのです。
西内 その時期ですとSiteCatalystですかね?
山内 はい。2007年にSiteCatalystを導入して、いかに成果を出すか、どういう記事が読まれていて、どういうサービスが使われているのかをひたすらレポートにするという取り組みからはじめました。レポートを出すことで、感覚に頼るのではなく、数字を見てサービスをつくるほうが成果が出るということを分かってくれる人が増えてきたんです。
そうして必然的に日経IDのプロジェクトに携わることになり、広告や販売にかかわっている営業メンバーと、どういうデータがあればもっと売れるのかを分析して、サービスを企画していきました。この10年は、集まったデータをどう生かすかという取り組みをしています。
データから直情的・直線的に判断しても成果にはつながらない
西内 いざデータを分析しようとしたとき、最初からスムーズにいったんですか?
山内 いいえ、もちろん紆余曲折がありました。そもそも、データを使うということがどんなことなのか、誰も分からないのです。当時はウェブ解析がブームでもあったので、まず可視化するということを中心にはじめました。可視化することで状況が見えてくると、編集側も販売店も広告営業している人も、そのデータを何かに生かそうと考える人が出てきます。必要性を分かってくれるので、レポートをもっと可視化しよう、人も増やそうという流れになって、10年ぐらいかかってやっとここまで来ました。
西内 だんだん興味を持つ方が増えてきたということですが、何かきっかけになったような成功事例があったのでしょうか?
山内 失敗事例の方が多いですね。
西内 それはそれで聞きたいです(笑)。
山内 最初のうちは期待に任せていろいろなものを可視化しました。そうすると何が起きるかというと、統制できなくなってしまうんですね。欲しいレポートは全部送る、SiteCatalystのアカウントが欲しい人にはとにかく配るというふうにしたら、スキル格差の問題が出てきたのです。
数字を見てミスリードする人もいれば、足し合わせても意味がない数字を足し合わせてしまう人がいたり。基本的な素養もない状態で拡大してしまったことで、データに溺れてしまうような状況が生まれたんです。レポートも多すぎて、活用する余裕がなくなるんですね。最初に理想を高く掲げすぎて、拡大しすぎたことが失敗でした。
もう一つ、当時のレベルでは、データをもとに施策をやってみてもなかなか成果が出ませんでした。たとえば当初、解約率を下げようと解約につながる要因を探す取り組みをしました。そうすると、「毎日サイトを訪れなくなった人は解約しやすい傾向にある」という要因を見つけることに成功しました。ところがサイトを毎日訪れなくなった人に、毎日メールを送るという施策を打ったところ、よけい解約が増えてしまったんです。
西内 サイトのことが意識から消えていた人に「そういえば登録していたな、解約しなきゃ」と思わせてしまったのですね。
山内 そうです。寝た子を起こすということが起きたのです。このように、データを見てそのまま直情的、直線的に判断しても、必ずしも成果に繋がらないという経験をたくさんしましたね。ストーリーや因果関係を意識して、ビジネスのゴールを見据えて組み立てなければいけないと気づくのに時間がかかりました。
次のステップでは、データをマーケティングにつなげる仕組みに取りかかりました。リアルタイムに近いかたちでデータを集め、そこに顧客属性も組み合わせてデータを深掘りしなければだめだと気づき、2011年頃からはじめたのが統合マーケティングシステムです。
具体的には、データや属性をもとに、その人がどういう行動をしているかを瞬時に理解するために必要なデータを集め、可視化するためのツールをつくりました。当時はまだデータウェアハウス(※)やプライベートDMP(※)という言葉も存在していなかったと思います。そうした時代に、意図せずプライベートDMPをつくりはじめたということですね。
※データウェアハウス:意思決定のために複数のシステムから必要なデータを収集し、目的別に再構成して時系列に蓄積した統合データベースのこと。
※DMP:Data Management Platformの略。さまざまなビッグデータや自社サイトのログデータなどを一元管理、分析して、広告配信など顧客とのコミュニケーションを最適化するためのプラットフォームのこと。
マーケティング視点でデータ活用が進むようになって、人も増えたのですが、まだまだ成果が出ませんでした。販売の担当者やマーケティングの担当者はデータを見てくれていたのですが、新聞社の本丸、つまりコンテンツやサービスを作る人にデータを見てもらわなければならない、という課題が上がってきました。デジタル関連の部署にいる人と、もともと記者職で日夜取材をしているような人とではスキルセットに大きな差があるので、そこをどう埋めるかという試行錯誤が長く続きました。
「オーディエンスエンゲージメント」を高める努力を
西内 編集や記者の方には、なかなかデータ活用が受け入れられづらい印象はありますね。
山内 やっぱりメディアって面白いなぁと思うんですけど、自分たちがこれだって思うコンテンツというのがあって、それを目立つところに配置して、読んでもらおうとするんですけれども、必ずしもそういう記事が読者に読まれるというわけじゃないんですよね。これは不文律であり、不都合な真実でもあると思うんですが。
芸能人のスキャンダル記事はよく読まれるのですが、普通に考えても、ある芸能人のスキャンダル記事がたくさん読まれるので、その関連記事や写真をひたすら掲載し会員登録を増やそうというのと、メディアの連続性をもってお客さんに受け入れられようとするのとでは、多分違った話です。
以前からここのギャップをどう捉えるかという話があって、解を出せないまま長い時間が経っていたのですが、いくつかの取り組みの中でこれを埋めるためのキーワードが出てきました。
1つの大きなきっかけは、欧米メディアの先行事例です。欧米では日本のような新聞宅配がないので、倒産する新聞社が出やすいんですね。その中で生き残ってきたWall Street JournalやNew York Times、Financial Timesが何をやったかというと、「顧客回帰」でした。顧客が何を求めているか、読者の価値というものを真剣に考え、「オーディエンスエンゲージメント」を高める努力をしました。
ユーザーの関わりをいかに増やすか。生活の中にメディアとの接点を持ってもらい、活用してもらうことによって接点を永続化する。その永続化した接点があるからメディアは生き残れるのだという当たり前のことなのですが、これまでが独りよがりだったということに気づきはじめたのです。
2015年にFinancial Timesは我々のグループに入ったのですが、見学に行った社員が、ちょっと彼らは今までと違うことをやっていると言うんです。何かよくわからないけどダッシュボード画面を映して、記事が読まれているかいないかをつぶさに観察しながらやっていると。そういう事例が出てきたことで、ようやく社内でもオーディエンスエンゲージメントが大事であると理解できたんです。
オーディエンスエンゲージメントの定義はそれぞれ会社ごとに違います。弊社にとっては、毎日読者の方に日経のサイトを訪れてもらって、解約せずに読み続けていただくことだと考えています。そのために、いろいろな行動データや属性データを統計分析しているのですが、年代が高くて、管理職で年収が高い、つまりは社会的地位が高い人たちが購読を継続してくださっているということがわかりました。ではなぜこの人たちに日経が必要かといえば、ビジネスに不可欠であると認識されているからです。もっとプリミティブな要素でいえば、そういう人たちの中でも、平日毎日サイトを訪れてくれる人は特に貢献度が高い変数であるといえるのです。
西内 サイトを訪れることが習慣化していると言えるんですね。
山内 そうです。いくつかの統計から、習慣化がはっきり見てとれました。サイトを訪れるタイミングも明確で、長年継続してくれているユーザーは、朝の6時から9時のあいだに1回、さらに昼または夕方にもう1回サイトを訪れています。かつ、その中でも記事の閲覧本数が多いほど継続率が高いという、この2つの要素が浮かび上がりました。
それを説明変数にしたエンゲージメント指標をつくって見せたところ、それまでは拡散しがちだった議論がその指標に集約されるようになりました。キャンペーンもコンテンツも、サイトを訪れて読んでもらえる、そしてそれが習慣化につながるようなサービスをつくればいい。あるコンテンツを企画しても、継続率に寄与してないのであれば意味がないとはっきり言える基準ができたことで、質についても評価できるようになりました。アクセス数だけでなく、読者にどう届けるかということが議論されるようになって、意思として受け入れようというかたちになったんです。
しかしながら、もう一歩難しいなと思うところは、やはり「読む」という行動が強く見えてしまうんですね。現場の記者からするとどうしても、アクセスが多い=いい記事だという意識があるので、質の評価についての探求は今後も続くと思います。
「入口」と「出口」で記事の役割を切り替えることで習慣化に導く
西内 芸能人のスキャンダル記事などでとにかく露出を増やして閲覧数を集めるというのは、ファネル(※)の入口としては大事であると思います。ただ、そればかりだと、ファネルの入口は広がってもコンバージョン(※)には至りません。継続率が高いロイヤルユーザーがよく見ている記事はどんなものなのか、コンバージョンにつながった記事ランキングを参考にして、ファネルの入口から出口まで、それぞれ明確に記事の役割を切り替えられるといいかもしれません。
※ファネル:漏斗のこと。転じてマーケティングにおいて、広く集客見込み顧客が、成約へ至る中で徐々に少数になっていくことを指す。
※コンバージョン:「転換」という意味。WEBサイトにおける目標到達となる行動のこと。この場合メディアサイトへの会員登録などを指す。
山内 全くその通りです。よくポートフォリオという言い方をしますが、獲得に向く記事、外部流入・外部拡散に向く記事、既存読者の満足度を高めるための記事、エンゲージメントに貢献する記事という、いくつかの記事の役割としての分類があります。
たとえば、4月は会員獲得の時期ですので、「1年目に知りたかった会計の基礎」という新入社員に向けた4月ならではの特集を組んだりして、若い読者にサイトチェックを習慣付けてもらうためのコンテンツづくりをしています。
もう少し経つと、今度は登録を解約する時期がくるんですね。統計的には1ヶ月目で10%、2ヶ月目で5%、3ヶ月目でまた5%ぐらい落ちるのですが、そこで減少率が落ち着いてきます。つまり、最初の3ヶ月が重要で、統計的に見ても入会した最初の数日というのは、習慣化するために重要です。その時期になると、今度はリテンションのコンテンツを提供する。習慣化に貢献するコンテンツや機能、サービスをこちらから仕掛けないといけないのですが、エンゲージメントを軸にして考えられるようになってきたのは大きいですね。
続きはこちら
西内啓(にしうちひろむ) 株式会社データビークル 最高製品責任者
東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教、大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長、ダナファーバー/ハーバードがん研究センター客員研究員を経て、2014年11月より株式会社データビークルを創業。自身のノウハウを活かした拡張アナリティクスツール「dataDiver」などの開発・販売と、官民のデータ活用プロジェクト支援に従事。著書に『統計学が最強の学問である』、『統計学が日本を救う』(中央公論新社)などがある。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)アドバイザー。
山内秀樹(やまうちひでき) 日本経済新聞社 編集局総合編集センター 部次長 兼 デジタル事業 デジタル編成ユニット 部次長
2000年日本経済新聞社入社。主にデジタル分野でのメディア立ち上げや運営に従事し、2010年の電子版創刊からはデータマーケティングの中心人物として、日経電子版の会員基盤である「日経ID」の企画・開発に携わるとともに、顧客データの分析やデータドリブンの普及活動を推進。メディアにおけるデータ活用やオーディエンスエンゲージメントの向上に取り組んでいる。今年4月より現職。